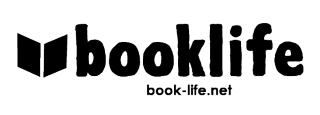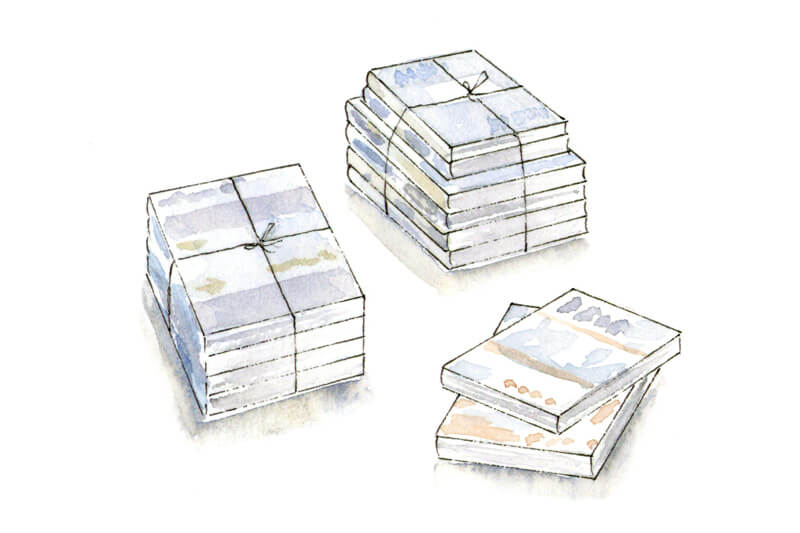こんにちは。みたっくす(@book_life_net)です!
本を処分するのではなく、寄付など何か役に立つ形をとりたいのですが…


本の引き取り額を寄付できるサービスはいかがでしょうか
要らなくなった本の引き取り額をそのまま寄付できるサービスがあることをご存知でしょうか?
それも寄付先は、貧困や教育といった社会課題の解決など様々あり、そうした買い取り業者が提携している支援団体先を自らで選択することができます。
昨今、身近な課題から大きな課題まで、社会の一員として自ら行動をしていかなくては変わらないということを痛感している人も多いのではないでしょうか。一方で、日本では欧米に比べ寄付の習慣が根付いていないため、寄付をしたくてもどのように行動をしていいのかわからないという方も多いと思います。
そこで今回は、だれでも気軽に始めることができる本を処分するという形での寄付についてご紹介します。
実は本を整理することが世の中を良くする行動につながるのです。
Contents
変わりつつある寄付マインド

そもそも寄付自体をほとんどしたことがなくて、どのような寄付の形があるのかもわかっていないのです…
どのように寄付したらよいかで悩んでいる人も少なくありません。それでも日本でも寄付の額も寄付先も増え続けている事実があります

日本ファンドレイジング協会の「寄付白書2017」によると、2016年の日本の個人寄付平均額は27,013円と書かれています。
年間で1人当たり約2500円。
一方でアメリカ人の年間平均額は、13万円です。
比較するべきことかわかりませんが毎月1万円以上寄付していることになります。
それでも2010年の日本の個人寄付総額4,874億円に対し、2016年には7,756億円と7年間で1.59倍に成長しています。(出典:寄付白書2017)
さらに新型コロナをきっかけに「コロナ給付金プロジェクト」が立ち上がり、その寄付額は2021年5月8日現在で約3億6千万円になっており、このプロジェクトをきっかけに寄付をしたという方もいるかも知れません。

寄付という活動を通して社会を良くしたい、本当に困っている人を助けたいという行動の現れが増え続けている。そのように受け取ることもできるのではないでしょうか。
一方で、「コロナ給付金プロジェクト」のような形で、社会の注目も集めつつ寄付できる形というのは決して多くはありません。また増え続けているとはいえ寄付するという行為が浸透していない社会において、どのように寄付をしたらよいかわからないという不安を抱えている方も少なからずいるのではないでしょうか。
そんな人に検討していただきたいのが本の処分による寄付の形です。
「本」で寄付するサービス


本で寄付するとはどのようなことでしょうか?
本の売却して得た費用をそのまま寄付する形のことです

昨今、自治体やNPO/NGO団体、それに大学などが本の買取業者と連携し、売却益を寄付してもらい、地域や社会課題を解決する費用に充てるサービスが増えてきています。
つまり不要になった古本の引き取り金額がそのまま寄付に当たり、社会貢献ができるという仕組みです。
寄付する先も多いところでは200件近くの中から選べるので、貢献したい課題に対して選択できるのも特徴です。
以下にて主なサービスを紹介しますので、詳しくは各サービスをチェックしてみて下さい。
「本」で寄付するサービス
チャリボン

本をきっかけに、世界をほんの少し、良い方向に変えていく。本をお送りいただく方々の存在があってこそ、私たちはそんな夢を描き続けれます。
あなたの本が、誰かの希望へつながる。古本で寄付をすることが、本を手放す時の選択肢のひとつとして、当たり前になるような社会になりますように。
公式サイト:ABOUT CHARIBON
古書ネット売買のバリューブックスが手掛けているサービスです。
寄付できる支援先は、2023年9月27日現在で84のNPO・NGO、95の大学、6の自治体の185団体※1あります。
数が多くて寄付先に悩んでしまいそうですが、「自然と共存」「医療・介護・福祉」などカテゴリ別から興味のある分野を探すことができます。
また各支援先ページには、具体的な○○円集まったらできることが記載されているので、寄付金がどのような形で具体的に使われるかがわかります。こうした詳細の説明のおかげで寄付する側はわかりやすく、判断しやすいと感じる方も多いのではないでしょうか。
ちなみにこれまでの支援実績は『総額:614,419,866円※2』と今回紹介するサービスの中で最大規模となる買い取り額を寄付しています。
※1,2.バリューブックス公式サイトより引用
-

-
本で寄付するチャリボン
 www.charibon.jp
www.charibon.jp
キモチと。

キモチと。は不要になったモノの買取金額で様々な団体等に寄付、応援、支援することができるブックオフの宅配買取サービスを活用した取り組みです。
引用元:「キモチと。」公式サイト
「キモチと。」は、BOOK-OFFとして広く知られるブックオフコーポレーション社によって提供されています。
このサービスの魅力は、本だけでなく使わなくなったあらゆるモノを買取の対象としており、その取り組みを通じて対象となるさまざまな団体やプログラムへの寄付が可能となる点です。
例えば、教育やアート分野など新型コロナの影響で困難な状況になっている団体の他、紛争や自然災害などより支援を必要としているプログラムなどがあります。

さらにこうしたプログラムがどのような目的や成果を達成しようとしているかは、詳細ページで確認することができます。
これにより、一般的な寄付活動が抱える「目的や成果が具体的に見えにくい」という課題を解消し、支援者自身が寄付先の活動を理解しやすくなっています。

寄付による貢献が明確になるので応援しやすくなりますよね
-

-
本で寄付できるブックオフ「キモチと。」
 www.bookoffonline.co.jp
www.bookoffonline.co.jp
もったいない本舗 寄付

「もったいない本舗」は古書の売買サービスを提供している企業ですが、それだけではなく時代の課題解決にも積極的に取り組んでいます。
現在、「もったいない本舗」を通じて査定された買取金額を、未来を切り開く子供たちと、失われつつある自然環境の保護に寄与することができます。寄付先は、様々な社会的な出来事に対して対象を追加しています。

具体的には、2019年の10月31日に発生した首里城の火災により、その多くが焼失した歴史的な建築を再建するための寄付活動を行いました。首里城は日本の歴史と沖縄の誇りを象徴していますが、その存在が一時的にも欠如することは、日本全体にとって大きな損失と言えます。そのような状況を鑑み、もったいない本舗は首里城再建のための寄付活動を支援しました。
さらに、2021年の2月には、我々が直面している新型コロナウイルスの問題に対し、医療従事者への寄付を始めました。この寄付は、感染拡大防止の最前線で戦い続ける医療従事者の支援を目的としています。
-

-
もったいない本舗|本を通じた寄付のご案内 【古本・本・CD・DVD買取いたします】
 www.mottainaihonpo.com
www.mottainaihonpo.com
ブックサプライ チャリティプログラム

ブックサプライ チャリティプログラムは、商品を査定し、その金額をブックサプライと連携している団体へ寄付します。
その支援活動は、世界中の子供たちへの援助が主となっており、ワクチン供給や難病と闘う子供たちへの援助といった具体的な形で実現されています。それぞれの子供たちが抱える問題に対し、ブックサプライは可能な限りの支援を提供し、未来を切り開くための一助となるべく行動しています。
ブックサプライのサイトを訪れてみれば、寄付者の皆さんが安心して貢献できるよう、透明性を重視した取り組みを心掛けています。例えば、寄付がどのように活用されているかを具体的に示すレポートや寄付証明書などを公開しています。

レポートなど活動状況が見えるのは安心しますよね!
-

-
ブックサプライ チャリティプログラム
 www.booksupply.jp
www.booksupply.jp
リサイクル基金 きしゃぽん

リサイクル募金きしゃぽんは、本・DVDなど、使い終わったものをリサイクル換金して寄付できる新しい募金のシステムです。
きしゃぽんとは
きしゃぽんのリサイクル募金システムは、古本やDVDなどの手元にある不用品を再利用し、その換金額を寄付するという新たな形のボランティア活動です。
募金の対象となる団体はなんと174もあり、特に「古本募金で母校を支援」をキーワードに掲げているため、きしゃぽんのリサイクル募金システムを利用することで、自分が卒業した母校に向けて直接的な支援を行うことも可能です。
自分が学んだ場所への感謝の気持ちを形にしたい、自分が育った環境を次世代に継承していきたいと考えている方には、温かみのある活動としてピッタリでしょう。

母校に支援をしたいとお考えの方はチェックしてみよう!
-

-
リサイクル募金 きしゃぽん
 kishapon.com
kishapon.com
本で寄付の仕方と注意点
どのサービスも基本的には古本をダンボールに詰めて指定の場所に郵送します。査定結果の金額を指定した団体へ寄付してもらえます。

詳しいやり方については各サイトを確認してみてください。
なお、どのサービスでも買取ができない本があることに注意が必要です。
ISBN(国際標準図書番号)がない本であったり、買取価格がつかない本であったりとその基準はサービスごとに異なります。

自宅にある本ならどれでも寄付になるというわけではないということは覚えておきましょう。
本で寄付することについて
寄付というと一方的にお金を渡す行為と思われがちですが、実はそのお金は循環しているだけでいつかいろんな形で返ってくるものです。
例えば、寄付に関してこんなお話を聞いたことがあります。
日本人が投資や寄付をあまりやりたがらないのも、自分と社会との一体感がなく、「自分の財布は自分だけのものだ」と考えているからではないでしょうか。
仮に1万円を寄付するとします。
すると、手元からは「1万円札」がなくなります。喪失感があるかもしれません。
けれど、もし寄付先との間に共有感があって、心理的につながっているのであれば、1万円は移動しただけで、「減っていない」ととらえることもできるはずです。
自分も他人もすべて一緒であり、何事も世の中のためになると思えば、投資や寄付も快くできるはずです。
お金を寄付した際には手元からお金がなくなるのは事実なので、このお話に実感が持てない方もいるかも知れません。しかし、お金ではなく本だったらいかがでしょう。
売った本が欲しい人へと渡り、またその人が売ればまた渡りという形で循環し、そうした本を読んだことがきっかけとなって新しい本が生まれて、また読む機会があると考えるとイメージできるのではないかと思います。
それはお金も一緒なのです。
つまり本を売って寄付するということは、本は欲している人へと渡り、さらに引き取り額は寄付という形で必要としている人たちへ届くという好循環が生まれるきっかけになるのではないでしょうか。
もし読んでいない本があって、処分を検討しているのであれば、今回紹介したサービスを利用して積極的に社会に貢献してみましょう。
寄付以外の前に本の整理や収納を検討したいという方には以下の記事では具体的な本の整理方法を紹介していますので、是非併せてご覧ください。
-

-
本の収納方法まとめ|本の仕分け方法からおすすめの本棚・グッズ・サービスを紹介
続きを見る
-

-
本棚整理のコツを4STEPで解説!本屋のような憧れの本棚へ
続きを見る